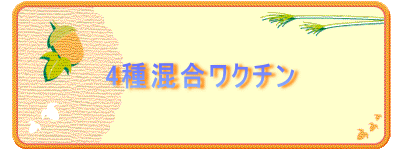
平成23年今月の病気
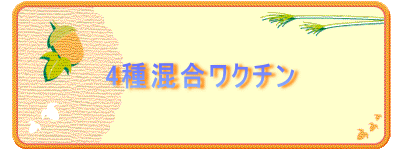
| H24年11月から、1種混合ワクチンの接種が始まります。今回使えるようになるワクチンは従来のジフテリア、百日咳、破傷風の3種混合ワクチンの中に、不活化ポリオワクチンが入ったものです。このワクチンは2回注射するところを、1回に減らすことができるので、赤ちゃんに与える痛みを減らす効果が期待されています。 使えるワクチンは2つあり、『テトラビッタ』と『クワトロパック』という名前で、ポリオ生ワクチンを不活化したものが入っています。現在、接種が行なわれている単独の不活化ポリオワクチンは『イモバックス』という名前で、実際に流行して病気を引き起こす野生のポリオウイルスを不活化して作られています。 3種混合ワクチンまたは単独不活化ポリオワクチンを1回でも接種すると、4種混合ワクチンを受けることができないため、11月まで待っている子供さんが見受けられますが、これは問題があります。乳児が百日咳に罹ると重症化しやすく、肺炎や脳症を起こして死亡することもあります。百日咳に対する免疫を早くつけるという意味でも、3ヶ月を過ぎている子どもさんは、11月に出る4種混合ワクチンを待たずに、3種混合ワクチンと単独不活化ポリオワクチンの接種を受けることをお勧めします。 |

| ★赤ちゃんの目を見ながら、授乳してください。 | |
| 2010年に福岡市北九州市福津市で行なわれた4ヶ月乳児健診のアンケート調査では、授乳しながら、TVやDVDを見る母親の割合は、よくするが29.3%、時々するが47.7%でした。また、授乳しながら、携帯電話やメールをする母親の割合は、よくするが4.7%、時々するが35.7%でした。 抱っこ、授乳、おむつ替えなど赤ちゃんはお母さんとのやり取りの仲で、信頼関係が出来上がり、強い絆で結ばれるようになります。(母子相互作用)。授乳の時には、赤ちゃんは母親とアイコンタクトしながら、コミュニケーションを学んでいきます。授乳の時には必ず赤ちゃんの目を見ながら おっぱいをあげてください。 |
|
| ★2歳までは、テレビ・ビデオの視聴を控えましょう | |
| 1歳6ヶ月児で、テレビ・ビデオの視聴時間と言葉の遅れを調べた結果、視聴時間が2時間未満の子では言葉の遅れが2.1%だったのに対し、2~4時間では4.6%、4時間以上では9.6%に言葉の遅れがみられました。 子どもは、親子で直接対話することで、言葉や感情表現などを学習します。テレビは見るだけで、互いの働きかけがないため、対人関係の発達に悪影響を及ぼします。言葉の発達が遅れる、表情が乏しい、視線が合いにくいなどの弊害が出ます。 2歳までのテレビ・ビデオ視聴は控えましょう。2歳過ぎても視聴時間は長くならないように!!テレビに子守をさせないで!!です。 |
|
| ★日本小児科会では以下の提言をしています。 | |
| ①2歳までのテレビ・ビデオ視聴は控えましょう。 ②授乳中、食事中のテレビ・ビデオの視聴はやめましょう。 ③すべてのメディアへ接触する総時間を制限することが重要です。1日2時間までを目安と考えます。テレビゲームは1日30分までを目安と考えます。 ④子ども部屋にはテレビ・ビデオ・パーソナルコンピューターを置かないようにしましょう。 ⑤保護者と子どもでメディアを上手に利用するルールを作りましょう。 |
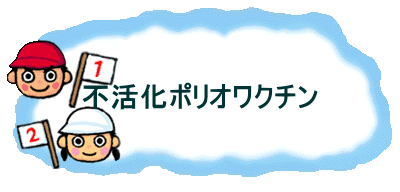
| 9月1日から、ポリオワクチンが生ワクチンから不活化ワクチンに変わります。生ポリオワクチンは、2回飲むだけで免疫がつく効果の高いワクチンでしたが、ポリオのような麻痺を100万回に1回程度の割合で起こすことが問題になっていました。今回使えるようになった不活化ポリオワクチンは、ポリオ様麻痺を起こすことなく、安全性に熟れたワクチンです。 | |
| ワクチンの対象年齢 | 接種対象年齢は、生後3ヶ月から90ヶ月(7歳半)までです。 |
| ワクチンの接種方法 | ①ポリオワクチンを1回も受けてない場合は、不活化ポリオワクチンを4回注射します。3~8週間の間隔をあけて3回接種したあと、6ヶ月以上あけて 4回目の接種を行ないます。 1回目→3~8週間あけて→2回目→3~8週間あけて→3回目→6ヶ月以上あけて→4回目 |
| ②今までに生ポリオワクチン接種を1回受けている場合は、不活化ポリオワクチンを3回注射します。生ワクチン接種後4週開けて1回目を接種し、3~8週あけて2回目、6ヶ月以上開けて3回目の接種を行ないます。 経口生ワクチン→4週間以上あけて→1回目→3~8週間あけて→2回目→3~8週間あけて→3回目 |
|
| ③今までに生ポリオワクチン接種を2回受けている場合不活化ポリオワクチンの接種は不要です。 | |
| ④今までに不活化ポリオワクチンの接種を受けている場合、不活化ポリオワクチンの接種回数が合計4回になるように追加接種します。 | |
| これまでと 変わった事 |
①生ポチオワクチンは、春と秋に季節が限定されていましたが、不活化ポリオワクチンは1年中いつでも受けることができます。 |
| ②3種混合やヒブなど 他のワクチンとの同時接種も可能です。 | |
| ③愛媛県内であれば、住んでいる市町村以外の医療機関でも接種可能です。 | |
| ワクチンの副反応 | 注射部位の痛みや発赤腫脹など軽微なものが ほとんどです。発熱(37.5℃以上)は約15%にみられます。非常にまれですが、重大な副反応として、ショックや けいれんが現れることもあります。 |
| 4種混合ワクチン | 11月からは4種混合ワクチン(従来のジフテリア・百日咳・破傷風の3種混合ワクチン+不活化ポリオワクチン)接種も始まります。ただし、3種混合ワクチンを1回でも接種したことがある場合は、4種混合ワクチンをうけることはできません。 |
| *ワクチンの種類が増えたため、乳児期の接種スケジュールが過密になっています。ワクチンについてわからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。 | |
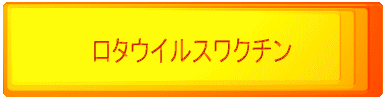
| 今年の11月21日からロタウイルスワクチンが使えるようになりました。 | |
| ロタウイルス胃腸炎とは? | ☆ロタウイルスが原因で起こる感染性胃腸炎っです。 ☆冬から早春(2月から4月)に流行します。 ☆乳幼児がかかる病気で、1歳までに1/3、5歳までにほぼ100%の子どもが罹ります。 ☆激しい嘔吐と白色水様下痢(昔は『白痢』とも呼ばれました)がみられます。高熱を伴うこともあります。 ☆ノロウイルスなど、他のウイルス性胃腸炎より症状が強く、脱水になりやすいのが特徴です。 ☆国内で年間約79万人が小児科を受診し、約10%が入院します。合併症として、脳炎・脳症を起こすことがあります。 |
| ロタウイルスワクチン | ☆ロタウイルスは何回も人に感染しますが、初回の感染時に重症化しやすいことがわかっています。 ☆このワクチンはロタウイルスの病原性を弱めた生ワクチンで発症や重症化を予防します。 |
| ロタウイルスワクチンの接種方法 | ☆このワクチンは飲むワクチンです。(注射ではありません)1回1本(1.5ml)のワクチンを4週間以上の間隔をあけて2回飲みます。生後6週から接種可能で、遅くとも24週(生まれた日を0日として168日)までに2回目の接種を終わらせる必要があります。そのため、1回目を生後20週(140日)までに受ける必要があります。 当院の接種料金は1回12500円です。 |
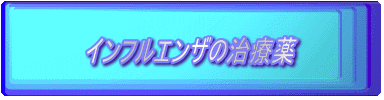
| 平成13年にタミフルが使えるようになってから、インフルエンザの症状を軽くすることができるようになりました。現在、4種類の薬がありますが、いずれもタミフルと同じ薬効の薬です。 | |
| タミフル | 薬の種類:カプセルとドライシロップがあります。小児はドライシロップを使いますが、体重が37.5㎏以上あればカプセルでもOKです。朝と夕の1日2回、5日間 内服します。 注意点:異常行動を起こす可能性があるので、10代は原則的にタミフルを使いません。ただし、喘息があるためにリレンザが使えないなどの理由がある場合は10代でもタミフルを使うことは可能です。リレンザ耐性ウイルス(Aソ連型)が問題になったことがありますが、現時点で耐性ウイルスを気にする必要はありません。 |
| リレンザ | 薬の種類:ディスクに入った乾燥した粉末を専用の吸入器で吸入します。喘息の時に使う吸入器(ネブライザー)で吸入することもできます。(ディスクから取り出して、生理食塩水で溶解して吸入管に入れてセットします。)薬を飲まない子どもさんには これが便利です。朝と夕の1日2回、5日間吸入します。 注意点:喘息のこどもさんでは、発作を誘発することがあります。 |
| イナビル | 薬の種類:容器に入った粉末を吸入します。10歳未満は1本、10歳以上は2本吸入します。水に溶けないのでリレンザのようにネブライザーで吸入することはできません。1回吸入するだけでよいのが特徴です。 |
| ラピアクタ | 薬の種類:点滴で使う注射剤です。15分以上かけて点滴します。点滴は1回だけでよく、吐き気が強くて薬が飲めないような時に使います。 |
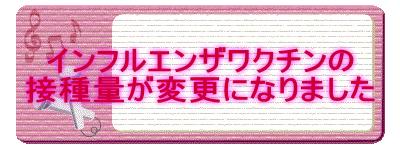
従来のインフルエンザの接種量は少ないと指摘があり、ワクチンの効果を高めるため増量が検討されていました。
今年から接種量を増やすことになりました
| 従来 | |
| 生後6ヶ月以上1歳未満 | 1~4週間で0.1mlを2回接種 |
| 1歳以上6歳未満 | 1~4週間で0.2mlを2回接種 |
| 6歳以上13歳未満 | 1~4週間で0.3mlを2回接種 |
| 13歳以上 | 0.5mlを1回接種 |
↓
| 今年から | |
| 生後6ヶ月以上3歳未満 | 2~4週間間隔で0.25mlを2回接種 |
| 3歳以上13歳未満 | 2~4週間で0.5mlを2回接種 |
| 13歳以上 | 0.5mlを1回接種 |
このように小児の接種量が増えることになりましたが、東日本大震災でワクチン工場が被災したことなどから、ワクチンメーカーから医療機関に納入されるワクチンは前年並みになる見込みです。
当院でも、ワクチンの確保に努めていますが、当院に納入されるワクチンは成人量で2200回分になりそうです。
申し訳ありませんが、この量になりましたら予約を打ち切りますのでご了承ください。
その後、追加でワクチンが確保できましたら、その都度予約を受け付けることに致します。
当院は小児のワクチン接種を優先したいと考えておりますので、成人の方はできるだけ内科でワクチン接種を受けてください。
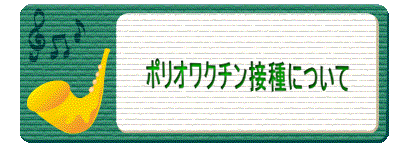
| ポリオ(小児まひ)は、ポリオウイルスにより引き起こされる感染症で、1%未満の確率で運動麻痺が後遺症として残り、麻痺を治すことはできません。日本では昭和30年頃に大流行しましたが、昭和56年以降発症していません。しかし、今でもパキスタン、アフガニスタン、インド、ナイジェリアの4ヶ国で流行が続いており、ウイルスが国内に持ち込まれる可能性があります。予防のためにワクチン接種が不可欠です。 | |
| ポリオワクチンには、現在日本で使われている生ワクチンと、外国で使われている不活化ワクチンがあります。 生ワクチンは①飲むワクチンなので痛くない②ポリオが流行している地域では、不活化ワクチンよりも効果がある といった良い点がありますが、ワクチンからポリオを発症(これをワクチン関連麻痺性ポリオという)する危険性があります。発症は国内では年間1~4人報告されており、約200~486万接種あたり一人の割合で発症します。計算上、県内での発症は100年に1人で、なる確率は非常に低いのですが、発症してしまうと治療法がなく、一生麻痺が残ります。(昨年NHKで これを取り上げた番組が放送されて大きな反響がありました。) そのため、多くの国ではワクチン関連麻痺性ポリオが起こらない不活化ワクチンが使われています。現在、日本では不活化ワクチンが承認されていない(*平成24年度中に使用できるよう、治療研究が進められている段階です。)ため、不活化ワクチンを接種する場合は、外国から個人輸入したものを、個人の責任で接種することになります。 よって、不活化ワクチンの接種を受ける場合は、①国の補助を受けられないので有料になる②健康被害が出た場合は国が責任をとってくれない(輸入ワクチン副作用被害救済制度はあるが、一時金が出るのみで、医療費や障害年金などの支給はない)③注射による痛みや副反応(アレルギー反応、発熱、注射部位の発赤や腫れなど)が起こる可能性がある、という問題点があります。 外国では安全と言われているワクチンですが、健康被害が出ても それに対する保証はありません。この点をよくお考えください。 当院では、不活化ワクチンの輸入はしておりませんが、不活化ワクチンを希望される方が多いようなら輸入を考えます。手続きが必要ですので、輸入できるようになるには1ヶ月ほどかかります。 |
|
| 輸入ポリオ不活化ワクチンについて | 現在、日本に輸入されているのはサノフィパスツール社のIMOVAX PORIOです。原則的に大腿部への筋肉注射が行なわれます。 |
| 接種スケジュール | 一回目(生後2ヶ月)→二回目(生後4ヶ月)→三回目(1歳から1歳6ヶ月)→四回目(4~6歳) 一回目(3ヶ月以降の場合)→二回目(4~8週間後)→三回目(2~8~14ヵ月後)→四回目(4~6歳) |
| *すでに1回目生ワクチンを接種している場合 一回目(生ワクチン接種から2ヶ月以上)→二回目(8週間後)→三回目(4~6歳) |
|
| *不活化ワクチン2回目接種後に生ワクチンを2回飲む方法 一回目・・不活化・・(生後2ヶ月)→二回目・・不活化・・(生後4ヶ月)→三回目・・生・・(2~6ヶ月後・・・遅くても1年以内)→四回目(4~6歳)
|
|

| ワクチンの品不足から、子宮頸がんワクチンの公費接種(無料)が高校1,2年生に限定されていましたが、7月20日から中学生も公費接種ができるようになりました。 |
| 子宮頸がんワクチンは初回接種後の1ヶ月後に2回目、6ヵ月後に3回目の摂取が必要です。全部で3回接種しないといけないのですが、公費の補助を受けるためには 3回目を来年3月までに終了する必要があります。 そのためには、遅くとも 9月中に初回接種を済ませる必要があります。 子宮頸がんワクチンを希望される方は、なるべく早く予約されることを お勧めします。 |
| 子宮頸がんワクチンは 利き手でない側の肩の筋肉に注射します。長袖では注射しにくいので、ノースリーブか袖の短い半そでシャツで来院ください。暑い期間は問題ないのですが、寒い時期には長袖シャツの下にTシャツを着て来院していただけると助かります。 |
| 注射後にアレルギー反応が出ることがあるため、30分院内で待機してから お帰りください。接種した日は激しい運動は避けてください。 |
| 接種したところが、赤くなったり腫れたりすることがありますが、徐々にちいさくなり消失します。 |
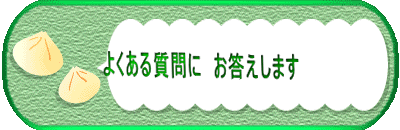
| Q.手のひらが黄色いのですが、黄疸では? | A.みかんなどの かんきつ類や、人参・かぼちゃ・パセリ・マンゴー・とうもろこし などのカロテンを多く含む食品をたくさん食べるとカロテンが皮膚に沈着し、皮膚が黄色くなります。特に手のひらや足の裏が黄色くなりますが、ひどくなると全身が黄色くなります。肝障害などで起こる黄疸では、眼球結膜(白眼の部分)が黄色くなりますが、柑皮症では眼球結膜は黄色くならないので区別できます。 黄疸が疑われる場合は、血液検査でビリルビン値を調べます。 柑皮症は みかんをよく食べる愛媛県民によくみられます。最近は人参ジュースが原因のことも多いようです。特に治療の必要はありませんが、柑橘類や人参を止めれば治ります。 |
| Q.赤ちゃんの親指が曲がったまま伸びません | A.乳幼児の指が曲がったままで、自分では伸ばせない状態を「ばね指」といいます。親指に多くみられます。診察時に伸ばしてあげることはできますが、しばらくすると また曲がったままになってしまいます。 指の腱が腫れて、腱鞘(腱のトンネル)を通ることができなくなるために起こります。 約8割が3~4年で治ります。指をのばして装具をつけると半年ほどで治ります。 |
| Q.赤ちゃんが脚をよくビクビクさせます | A.赤ちゃんは よく腕や脚をビクビクさせます。これは不随意運動(ミオクローヌス)というものです。大人でも、疲れた時や眠くなったときに体が勝手にビクッとなりますが、これがミオクローヌスです。 片側のこともあれば両側のこともあります。寝入りばなや ちょっとした刺激の後などにみられます。 ほとんどの場合は問題ありませんが、表情が硬かったり、長く続いたり発達の遅れを伴ったりする場合は異常があることがあるので、受診が必要です。 気になる場合は デジカメで撮影してから受診ください。 |

| 「朝起きたらシーツが血まみれだった」とあわてて外来に来られることがあります。これは夜中に無意識に鼻をこすったことで、鼻血が出てシーツについたために起こったことで、小児にはよくあることです。 | |
| 「多量の血を吐いた!胃潰瘍ではないか?」ということで、もっとあわてて来られることもあります。診てみると鼻血を多量に飲み込んで、それを吐いたためだったなんてこともあります。 | |
| Q.よく鼻血が出るのですが、異常ではないでしょうか? | A. 小児の鼻の入り口から2cm位までの所に毛細血管がたくさんあるので、簡単に鼻血が出ます。鼻をちょっとこすったり、鼻くそをほじったりしただけでも鼻の血管が傷ついて鼻血が出ることがあります。アレルギー性鼻炎(花粉症)では鼻粘膜の血管がふえるなどの理由で鼻血が出やすくなります。 また、一度鼻の血管を傷つけてしまうと、ちょっとした刺激で鼻血が出てしまうので繰り返し鼻血が出るようになってしまいます。 このように小児では鼻血を繰り返すことが多いので、鼻血が出やすいというのは さほど心配することではありません。 |
| Q.鼻血には どう対処したらいいですか? | A. ①鼻血を飲まないようにするため、やや下を向かせます。(上を向くと血を飲み込んでしまう恐れがあります) ②鼻翼全体を深くつまんで圧迫止血します。(鼻内にティッシュを入れる必要はありません) ③鼻呼吸ができないので、口呼吸しながら圧迫を続けます。15分以内に止まればOKです。 |
| Q.映画で鼻血を出したヒロインが白血病と診断されるシーンをみました。悪い病気ではないでしょうか? | A. 鼻血がなかなか止まらない場合や出血斑、貧血(顔色が悪い)がみられた場合は血液の病気の可能性がありますので、検査が必要です。 白血病や紫斑病などの血液の病気では血を固まらせる働きのある血小板が減少するために出血しやすくなり、鼻血がみられます。このような場合は、鼻血がなかなか止まらなくなります。また、足に出血斑(赤くて圧迫しても退色しない発疹がみられます) |
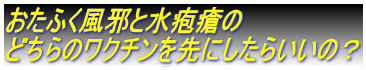
| ①水疱瘡は罹っても特効薬がある。 ②水疱瘡ワクチンは水疱瘡の人と接触してから72時間以内にワクチンを接種すると発症を予防できる。 ③おたふくかぜのワクチンは、おたふく風邪の人と接触してからワクチンを接種しても発症予防することはできない。 以上の理由から、みずぼうそうが大流行している場合を除いて、おたふくかぜのワクチンを先に接種することを お勧めしています。 |
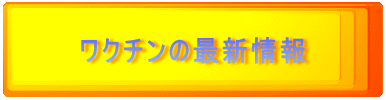
|
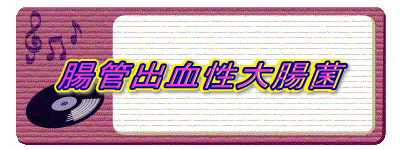
| 腸管出血性大腸菌って何? | 大腸菌のほとんどは人に無害ですが、大腸菌の中には、人に下痢や腹痛などの症状を起こすものがあり、これらを「病原性大腸菌」と呼びます。その病原性大腸菌の中で赤痢菌のような毒素を産出し、多量の血便を引き起こすものが『腸管出血性大腸菌』です。 大腸菌の菌成分の「O抗原」により いくつかに分類されています。『腸管出血性大腸菌』の代表的なものは「O157」で、その他に今回ユッケ食中毒で有名になった「O111」や「O26」、「O128」、「O145」などがあります。 『腸管出血性大腸菌』は牛などの家畜から時々見つかります。家畜では症状が出ない事が多く、外見からでは家畜が菌をもっているかどうか判断することはできません。 |
| どのような症状がでるの? | 3~8日の潜伏期間の後に水様便で発症し、さらに激しい腹痛と多量の血便がみられるようになります。発熱はないか、あっても軽微です。激しい腹痛と血便がある場合は『腸管出血性大腸菌』が疑われます。 このような症状が出た人の6~7%で発症の2週間以内(多くは5~7日後)に溶血性尿素症症候群(HUS)や脳症などの重症合併症が発症すると言われています。ただし、軽症の場合や症状がほとんどないこともあります。 |
| どんな検査・治療をするの? | 便の細菌培養検査を行ないます。『腸管出血性大腸菌』が見つかれば、診断が確定します。入院し安静・輸液・抗生剤内服などの治療を行ないます。 |
| どこからうつるの? | 『腸管出血性大腸菌』に汚染された肉・水・野菜を食べることで感染します。国内では北陸の焼肉店で起きた事件のように、食肉を生や加熱不足で食べて感染する事例が多く報告されています。 海外では、生野菜を食べて感染した事例も発生しています。米国では、生のホウレンソウによる食中毒があり、菌を持つイノシシが農場を汚染したと推測されています。 |
| どのように予防すればいいの? | 『腸管出血性大腸菌』は熱に弱く、75℃で1分間以上加熱すると死滅します。しかし、低温には強く、家庭の冷凍庫では生き残ると考えられています。また、水中では相当長期間生存します。 少しの菌(100個ほど)で発病してしまうため、菌が食物で少し増えただけで感染源になってしまいます。 肉については生食を避けて、よく加熱(中心部まで十分に加熱)して食べれば大丈夫です。生で食べる野菜や果物は新鮮なものを購入し、冷蔵庫で保存し、流水で十分に洗ってください。湯がき(100℃の湯で5分程度)が有効であるとされていますので、ブロッコリーやカリフラワーなどの形が複雑なものは熱湯で湯がいてください。 *手や調理器具を流水・洗剤で十分に洗ってください。 *生肉が触れた まな板や包丁・ふきん・食器は熱湯等で十分消毒してください。 *生肉が触れた まな板・包丁を使って、生で食べる野菜を調理してはいけません。 *調理した食品は すみやかに食べてください。 電子レンジで調理する場合、食品全体をむらなく75℃で1分間以上加熱すれば菌は死滅しますが、単に温めるだけでは菌は死滅しないので注意が必要です。 |

| スプーン爪 | 爪は通常、上に凸になっていますが、爪がスプーンのように凹んでいる状態のものを スプーン爪といいます。 乳幼児の爪は非常に軟らかいため、ほとんど乳幼児はスプーン爪になっています。大きくなるにしたがって、爪が硬く厚くなっていき、上に凸の爪に変わっていきます。よって、乳幼児のスプーン爪は異常ではありません。ごくまれに思春期まで続くことがありますが、通常、小学校入学ごろには治ります。学童期以降でスプーン爪がみられた場合、その原因のほとんどが鉄欠乏性貧血ですので、貧血の検査が必要です。その他の原因として外から力が爪にかかる場合、乾癬などの皮膚疾患があります。 |
| 爪の白濁 | 爪に白い斑点がみられることがあります。多くは爪に対する外傷原因で放置しておいてかまいません。白い斑点が広がって、爪が白く濁ったようになった場合は、小児でも爪白癬(爪のみずむし)のことがあるので、皮膚科で検査を受けてください。 |
| 爪の黒褐色の色素沈着 | 黒褐色の縦の筋ができた場合、乳幼児では「ほくろ(母斑)」が原因になっていることがほとんどで、成長と共に消失します。思春期にできた場合は悪性のこともあるので、皮膚科を受診してください。複数の爪にできた場合は遺伝性の病気やホルモン異常が原因のこともあります。 外傷などで爪の下に出血した場合は、出血でできた斑点が徐々に爪先の方に移動していって、自然になくなります。 |

| 生後6ヶ月までの赤ちゃんは、うまく排便できない(うんちをするのが下手)ために便秘になることがよくあります。通常は綿棒浣腸などで出るようになりますが、それでも なかなか出ない場合は治療が必要な場合もありますので遠慮なく受診してください。 | |
| 肛門狭窄 | 肛門と直腸の境目のところが生まれつき狭いことでおこる病気です。 症状:生後1~3ヶ月から便秘が始まる。1週間ほど便が出ず、綿棒刺激や浣腸でやっと便が出る。赤ちゃんが排便時に非常にいきむ、顔を真っ赤にしていきむ。 診断:肛門から小指を入れて、狭いところがないかを確認します。小指が入りにくい場合、肛門狭窄と診断されます。 治療:肛門から指をいれることを繰り返して狭い部分を広げます。 |
| ヒルシュスプリング病 | 腸管内には腸を動かす働きをする神経細胞が入っていますが、この神経細胞が生まれつきない腸管ができてしまうと、その部分の腸が動かないため。その部分で腸閉塞を起こします。5000人に1人の割合で発症します。X線造影検査などで診断し、神経細胞がない腸管を切除する手術が行なわれます。 通常、生後1ヶ月以内に、ひどい便秘・おなかの張り・嘔吐などの症状で発見されますが神経細胞のない腸管が非常に短い場合は「がんこな便秘」のみの症状で乳幼児期以降に見つかることもあります。がんこな便秘が続く場合は この病気の可能性もあるので一度ご相談ください。 |
![]()
| 舌の下から口腔底の伸びているスジ状のものを「舌小体」と呼びます。この舌小体は通常、舌の根元から中央まで付いていますが、この病気では生まれつき舌小体が舌の根元から舌先まで付いているため舌の機能がそこなわれます。 | |
| 症状 | ①話言葉が舌足らずで不明瞭になる ②うまく噛めない噛まない ③うまく飲み込めない・・・そのため水分を利用して流し込み食べをする傾向がみられる ④もどしやすい ⑤歯磨きを自分でするのは嫌がらないが、人にされるのは嫌がる |
| 今までは、言葉の問題だけが注目されていましたが、最近は食べる機能障害が注目されるようになっています。哺乳がうまくできない赤ちゃんや、小食で体重の増えの悪い子どもさんのなかに この病気が隠れていることがありますので、そのような場合は 舌の動きをチェックする必要があります。 | |
| 判断基準 | ①舌を前に出した時に、ハート型にくびれる ②口絵お開けて舌を上唇に触れさせると下顎が舌とともに上にあがる ③舌を上唇に触れさせると舌の先が下を向く |
| 治療 | 耳鼻科か口腔外科(小児歯科)で舌小体を整形する手術を行ないます |
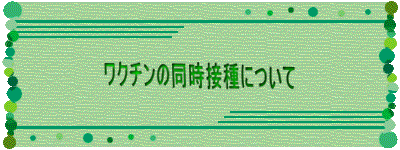
| ヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチンは3種混合ワクチンと同時接種が可能です。MRワクチンとの同時接種も可能です。 BCGとポリオについては当院では同時接種を行なっておりません。1回に2種類または3種類を同時に接種しますが、どのように接種するかは家族の方と相談してから行ないます。 |
|
| 例1 | BCG(3ヶ月健診)→4週間以上あける→ヒブ①+肺炎球菌①→4週間以上あける→ヒブ②+3種混合①→3週間以上あける→肺炎球菌②+3種混合②→3週間以上あける→ヒブ③+3種混合③→1週間以上あける→肺炎球菌③(9ヶ月検診) |
| 例2 | ヒブを早く接種する方法 ヒブ①+肺炎球菌①(生後2ヶ月から可)→4週間以上あける→ヒブ②+肺炎球菌②→1週間以上あける→BCG(3~4ヶ月健診)→4週間以上あける→ヒブ③+3種混合①→3週間以上あける→肺炎球菌③+3種混合②→3週間以上あける→3種混合③ |
| 例3 | 3つを同時に接種する方法 BCG(3ヶ月健診)→4週間以上あける→ヒブ①+肺炎球菌①+3種混合①→4週間以上あける→ヒブ②+肺炎球菌②+3種混合②→4週間以上あける→ヒブ③+肺炎球菌③+3種混合③ |

| 赤ちゃんの便から血が出たということで、あわてて受診されることがあります。赤ちゃんの血便の原因は色々ありますが、お腹を痛がる様子がなければ、あわてることはありません。便(おむつ)を持って受診ください。必要に応じて便の細菌培養検査などを行ないます。 | |||
| 原因 | ①ビタミンK欠乏症 | 通常、生後2ヶ月までの乳児にみられます。母乳栄養の子に多くみられます。この病気を予防するために、産婦人科でビタミンKのシロップを生後すぐと生後1ヶ月に飲ませます。高度の肝機能異常がない限り、これで予防可能です。 | |
| ②腸重積 | 腸の中に腸が入り込む病気で、4ヶ月から1歳半くらいまで(2歳以上はまれ)の子どもにみられます。いちごゼリーのような血便がみられます。強い腹痛がみられ、激しく泣いたり、治まったりを繰り返します。顔色不良や嘔吐もみられるようになります。造影剤や空気を肛門から加圧して入れて、腸の中に入り込んだ腸を元に戻す治療が必要で、緊急を要します。うまく入らない場合は手術が必要です。 | ||
| ③裂肛 | 硬い便の表面に血がついたり、排便後に血が肛門から出たり(肛門をふいた紙に血がつく)します。離乳食が始まって便が硬くなってくるとよくみられます。便を軟らかくすると軽快します。 | ||
| ④細菌性腸炎 | 病原性大腸炎、サルモネラ、キャンピロバクターなどの細菌の感染によって起こります。あらゆる年齢でみられます。乳児の血便でも、便培養検査を行なうと、病原性大腸菌が割りとよく検出されます。抗生剤の内服や整腸剤で治療します。 | ||
| ⑤ | ミルクなどの食物アレルギーで血便が出ることがあり、ミルクの除去などにより軽快することがあります。 | ||
| ⑥ | 2ヶ月から6ヶ月頃までの母乳栄養児では、便の中に点状またはスジ状の血液が少し混じるということがよくあります。その理由は以下のように考えられています。 母乳中に含まれる乳糖が腸内で発酵する ↓ 腸内が酸性に傾き、腸管ガスが増加し、腸の動きが活発になる ↓ 強い酸性や腸管ガスの増加が腸管粘膜を刺激して粘膜が充血する ↓ 点状の出血を起こして血便がみられる 赤ちゃんが元気で機嫌がよく、哺乳も良好で嘔吐や発熱などの症状も無く、便に混じる血液も少ない場合は 、心配ありません。 |
||
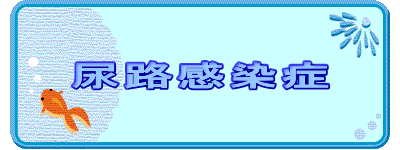
| 尿路感染症とは、腎臓・腎盂・尿管・膀胱・尿道のどこかに細菌やウイルスが感染して炎症を起こす病気です。原因のほとんどは 大腸菌などの細菌による感染です。尿道口(おしっこを出す出口)から細菌が侵入し、尿道→膀胱→尿管→腎盂→腎臓と上に向かって炎症が波及します。尿道の短い女児に多い病気ですが、乳幼児では男児にもみられます。夏にはアデノウイルスによる急性出血性膀胱炎もよくみられます。 | |
| 症状 | 頻尿や おしっこした時に痛み(排尿痛)残尿感がみられます。腎盂・腎臓に炎症がおよぶ(腎盂腎炎)と 高熱が出ます。症状を訴えられない乳幼児では、感染が上部に進み、腎盂腎炎になって高熱を出すまで感染に気づかないことが多い。 |
| 検査 | 尿の検査で、尿中の白血球が増えます。*おむつをしている子どもは採尿バッグで尿をとって検査します。腎盂腎炎では血液中の白血球が増加し、炎症反応(CRP)が高値になります。 |
| 治療 | 軽症では、抗生物質の内服で治療します。腎盂腎炎の場合は入院して抗生物質の点滴を行ないます。 |
| 尿路感染症で特に気をつけること | ①風邪症状がなく、のども赤く腫れてないのに高熱が出る場合は尿路感染症を疑って尿検査をする必要があります。特に乳幼児が高熱をだしているにもかかわらず、特に症状がない場合は必ず小児科を受診してください。 |
| ②腎盂腎炎を繰り返す場合、先天的な尿路の異常が原因になっていることがあります。尿路に造影剤を入れてレントゲン検査を行ないます。最も多いのは膀胱から尿路へ尿が逆流する「膀胱尿管逆流現象(VUR)」です。膀胱と尿管のつなぎめの構造に異常があると逆流が起きてしまいます。軽度なら成長に伴って自然に治ることもありますが、治らないと手術となります。 | |
| ③腎盂腎炎を繰り返すと腎臓そのものがダメージを受けて腎機能が萎縮してしまう危険性があります。したがって腎盂腎炎を繰り返す場合は早めに尿路の異常の有無を調べる必要があります。 | |