
今月の病気(平成16年)
12月

| 以前は『小型球ウイルスO』と呼ばれていたノロウイルスが原因で起こる胃腸炎です。冬に多く発生し、人から人に伝染します。また、カキやアサリなどの二枚貝から伝染することもあります。 | |
| 症状は? | 1〜2日の潜伏期間をへて、突然 吐き始めます。その後、下痢が1〜3日続きます。まれに嘔吐や下痢がひどくなり、点滴を必要とすることがあります。 発熱は軽度で、出ても38度前後です。ロタウイルスによる白色便性下痢症とに比べて軽症です。 |
| 伝染しやすいため注意が必要 | 非常に伝染しやすいので注意が必要です。この病気にかかると約1週間便からウイルスが排出されます。また、吐物中にもウイルスがいます。便や吐物を始末する時、手、雑巾、バケツ、洗い場などがウイルスで汚染され、それらを介して伝染します。また、乾燥するとウイルスが空気中に漂って伝染します。 |
| 予防方法 | 便や吐物は早めにペーパータオル等でふき取り、ビニール袋に密封廃棄してください。 |
| 便や吐物で汚れた床は、家庭用塩素系漂白剤を含ませた雑巾でふいて消毒してください。 | |
| 紙おむつや お尻ふきは ビニール袋に密封して捨ててください。 | |
| 手は十分水洗いしてウイルスを洗い流しましょう。 | |
| 嘔吐下痢の症状のある人は調理しないようにしましょう。 | |
| *ノロウイルスには次亜塩素酸ナトリウムは有効ですが、アルコールや逆性石鹸は無効です。便や吐物を始末する時に使った雑巾や用具は家庭用塩素系漂白剤を60倍に薄めて5〜10分つけ置きして消毒してください。 | |
| *ノロウイルスは生牡蠣による集団食中毒の原因としても有名ですが、熱に弱いウイルスなので85℃異常で1分間加熱して食べれば大丈夫です。 | |
11月
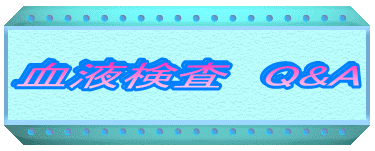
当院ではABO型とRh型の検査をおこなっています。検査は保障がきかないので自費となり、
当院では800円(消費税込)です。
検査は少量の血液検査でできるので、指先か耳たぶから血液をとります。
所要時間は数分です。
![]() 血液検査は いつ受けるのがよいでしょうか?
血液検査は いつ受けるのがよいでしょうか?
赤ちゃんが病気をしないようにするため、妊娠中のお母さんから免疫物質がへその緒を通じて赤ちゃんに運ばれます。この免疫物質は生後1年くらいまで、赤ちゃん体内に残るのですが、この免疫物質が、血液検査に影響を及ぼし、間違った結果を出すことがあります。
したがって、血液検査をするのは、母親から免疫物質がなくなる1歳ごろがお勧めです。
![]() Rh型とは?
Rh型とは?
赤血球膜上のD抗体の有無を調べる検査です。D抗体があればRh(+)、なければRh(−)です。ほとんどの人はRh(+)ですが、日本人の場合200人に一人がRh(−)です。
Rh(−)の人にRh(+)の血液が輸血されると溶血反応を生じて死亡する危険があります。また、Rh(−)の女性がRh(+)の子供を出産すると、その次以降の出産で新生児溶血性黄疸を引き起こし、赤ちゃんが死亡する危険があります。したがって、ABOだけでなく、Rh型も検査しておきましょう。
10月

| どのようなインフルエンザに効果がありますか? | 今年流行すると予想されているA型2種類(ソ連型と香港型)、B型1種類に対して効果があります。昨年末から東南アジアで発生した新型鳥インフルエンザ(H5N1)には効果がありません。 |
| 2回接種しないといけないですか? | 13歳未満では2回の接種が必要です。65歳以上は1回の接種でかまいません 13歳から65歳では、昨年インフルエンザにかかった場合や毎年ワクチンしている場合は1回でもかまいませんが、より効果を高めたい場合は2回の接種をお勧めします。 接種間隔は1〜4週間とされていますが、4週間隔での接種が1番効果的ですので、4週間隔での接種をお勧めします。もし、風邪などで接種間隔が4週間を超えてしまっても、6週間くらいまでなら十分効果はあります。 |
| いつ受けるのがよいのでしょうか? | 接種後1ヶ月から効果が現れ、その効果は3〜4ヶ月間持続します。インフルエンザの流行が今年の年末から来年の4月までとすると、ワクチンを2回接種する場合、1回目は11月中旬までに、2回目は12月中旬までに受けることをお勧めします。 |
| 他のワクチンとの接種間隔は? | インフルエンザワクチンは不活化ワクチンですので、1週間すると他のワクチンを受けることができます。 *生ワクチン(ポリオ、BCG、麻疹、風疹、水痘、おたふくかぜ)を受けた場合は4週間しないと他のワクチンをうけることはできません。 *不活化ワクチン・・・(3種混合、日本脳炎、B型肝炎、インフルエンザ) |
| 何歳から接種できますか? | インフルエンザワクチン接種について年齢制限はありませんが、当院では生後6ヶ月からワクチンを接種しております。ただし、1歳未満ではワクチンの効果が少し低いので、家族全員がインフルエンザにかからないようにワクチンを接種することをお勧めします。 |
| 卵アレルギーがあるのですが | インフルエンザワクチンは鶏卵を材料に製造するため、ごく微量の鶏卵成分が含まれます。そのため卵アレルギーの人は注意が必要ですので、接種前に必ず申し出てください。 当院では卵アレルギーのため、卵の除去食をしている人に対しては皮内テストを実施し、陰性の場合のみワクチンを接種しています。 |
| 添加されているチメロサールの安全性は? | チメロサールは、不活化ワクチンの保存剤として添加されているもので、エチル水銀を含んでいます。この保存剤は1930年代から使用されていましたが、数年前に自閉症や神経疾患の発病に関係するのではないかと疑われました。米国医学協会は昨年5月に関係はないと結論を出しましたが、ワクチンに含まれる保存剤などの添加物はないにこしたことはありません。ワクチンメーカーはチメロサールの濃度を低くするようになり、昨年から低濃度のものに変更されました。チメロサールを含まない製品も作られるようになりましたが、大人用(0.5ml)のみで、少量しか生産されません。今年も、当院ではチメロサールの濃度の低いワクチンを使用します。 |
9月

| マイコプラズマ肺炎は『マイコプラズマ・ニューモニエ』という小さな細菌によって起こります。飛沫感染でうつり、1〜4週間の潜伏期間で発病します。潜伏期間が長く、ゆっくり発病するので、気づくのが遅れ、咳やくしゃみで細菌が撒き散らされます。家庭内や寮、学校、職場といった狭い範囲で散発します。 | |
| 症状 | 初めは普通の風邪と同じ症状ですが、その後に頑固な咳が長期間続くことが特徴で、夜間や早朝にひどくなる傾向があります。熱は高いこともありますが微熱程度のこともあります。吐き気・嘔吐・下痢などの消火器症状、、中耳炎、筋肉痛・関節痛、発疹、ごくまれに神経症状がみられることがあります。 |
| 年齢 | 5歳以上の幼児・学童・成人にみられます。5歳未満の乳幼児にも感染しますが、ひどくなりません。 |
| 診断 | しつこい咳と胸のレントゲン写真で特徴的な肺炎像があればおおよその診断がつきます。しかし、聴診器で聴いても肺炎の音が聞こえないことが多いので、発見が遅れることがあります。 確定診断には、血液中の抗体価が高くなるかどうかをみますが、診断に2週間以上かかってしまう(治ったころわかる)ため実用的ではありません。 最近、若干精度に問題はありますが、発病1週間で判定できる迅速反応キットが発売され、当院ではこれを使っています。 |
| 治療 | マクロライド系抗生剤(クラリスやジスロマック)やテトラサイクリン系抗生剤(ミノマイシンなど)を使います。 マクロライド系抗生剤は味がよくないので、飲ませるのに苦労します。 一般によく使われるペニシリン系やセフェム系の抗生剤(フロモックス、メイアクト、トミロン、セフゾン)は効果がありません。 |
8月
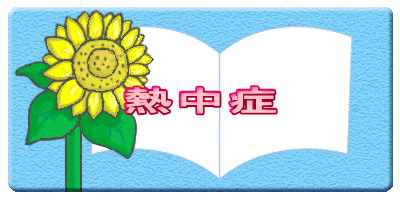
| 熱中症とは? | 高温環境下で発生する障害の総称で、腕や足の筋肉のこむらがえり、脱力感、倦怠感、めまい、頭痛、吐き気などがみられ、ひどくなると脳に異常をきたし、意識障害がみられます。 熱中症は、気温と湿度が高い時に起こります。特に急に暑くなった日に起こりやすく、梅雨の合間の真夏日は特に要注意です。 |
| 予防 | ①疲労、発熱、かぜ、下痢など体調の悪い時は熱中症になりやすいので暑い日中の外出や運動は控えましょう。 |
| ②服装は通気性や吸湿性の良いものにし外出時にはきちんと防止をかぶりましょう。 | |
| ③こまめに水分を補給しましょう。汗をたくさんかいた時は、塩分も失われるのでスポーツドリンクが良いでしょう。 | |
| ④気温が高い時は運動は控えましょう。運動をする場合は十分休息をとり水分を補給しましょう。 | |
| 熱中症になったかな? と思った時は |
①涼しい日陰やクーラーの効いた室内などに移動し衣類をゆるめて休んでください。 |
| ②うちわを使って風を送ったり、氷や冷水でぬらしたタオルをかけて体を冷やしてください。 | |
| ③スポーツドリンクで水分を補給してください。ただし、意識がはっきりしない時は、誤嚥する危険性があるので水分補給をしてはいけません。**よくならない場合は体を冷やしながら病院へ行きましょう. |
|
| ④意識がはっきりしない場合はすぐに救急車を呼んで病院へ行ってください。 |
7月

ラテックスアレルギーは、ラテックス(ゴムの木の樹液)によるアレルギーで、
接触皮膚炎・じんましん・喘息・重症例ではショック等の症状を呈します。
1980年代から増加し現在では小児にも発症がみられます。
| 症状 | ラテックス製品に触れることによっておこります。家事をする時にゴム手袋をしたらじんましんやしっしんが出たとか、ゴム風船を膨らませていたら唇が腫れたとか言う場合にはラテックスアレルギーが強く疑われます。 ラテックスアレルギーの人では果物や野菜にアレルギー反応を起こすことがあります。バナナ、キウイ、メロン、スイカ、桃、トマト、ジャガイモ、セロリ、なす、ピーナッツなどを食べて唇が腫れたり、下痢・腹痛などの症状を起こす場合はラテックスアレルギーを疑う必要があります。 |
| 治療 | ラテックス製品に接触しない様にすることが最も重要です。ラテックス製品は広範囲に使われています。特に歯科医院や病院ではラテックス製品を多く使っているので要注意です。上記の症状があれば検査を受けてください。 当院では採血をしてラテックスに対するアレルギー抗体(IgE)を調べています。危険なラテックス製品を避けていれば、日常生活は支障がありません。症状が強い場合は抗アレルギー薬を使用します。 |
| 予防 | ラテックス製品は身の回りに数多くありますが、ゴムの成分が溶けやすいものがアレルギーを起こしやすいといわれています。 哺乳瓶の乳首・・・・ゴム成分があまり溶け出さず、アレルギーをおこしにくくなっています。 おしゃぶり・・・おしゃぶりに使われているゴムは微量溶け出すので、アレルギーの人はやめましょう。 風船・輪ゴム・ボール・ゴムの人形・・・・溶け出しやすいのでできるだけ触らないようにしましょう。輪ゴムを指や腕に巻いたり、風船をしゃぶったりするのはやめさせましょう。 チューインガム・・・・・チクル(ゴムの一種)と酢酸ビニルのポリマーに味付けしたものです。やめさせたほうがよいでしょう。 |
6月

ダニは高温多湿を好むため、この時期に非常に繁殖します。
アレルギーのお子さんのいる家庭では、ぜひダニを減らす対策をとってください。
ダニを減らす対策
①布団に掃除機をかけよう。
②布団の丸洗い布団カバー、シーツはまめに洗濯しよう。
③枕はパイプ枕にしよう。そばがら枕はだめ。
④部屋の湿度は60%以下に。
⑤床はフローリングに。じゅうたんははずそう。
⑥ソファーは布張りはだめ。ビニール製か皮にしよう。
⑦ぬいぐるみは避けよう。
⑧カーテンは時々洗おう。
⑨ペットは飼わない方が無難。どうしても飼う場合はこまめにシャンプーをしよう。
*ダニの殺虫剤は床のダニを減らしますが、生き残ったダニがすぐ増えるので効果は長続きしません。
*空気清浄機は空気中の埃は減りますがこれだけではダニ対策にはなりません。
5月
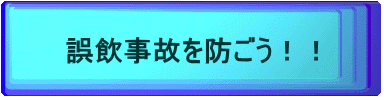
もしも危険物を誤飲してしまった場合、まず電話で いつ 何を どのくらい飲んだかを連絡してから受診ください。
誤飲事故を防ぐためのポイント
①危険物をなくす。②危険物を子供の周りに置かない。③危険物を子供の手の届かないところに(床から1m以上の高さの場所)におく。④危険物を子供では開かない箱や引き出しに入れる。
| ホウ酸団子 | ホウ酸は1〜3g食べるだけで中毒症状がでます。自家製のホウ酸団子一個には小児の経口致死量に相当するホウ酸がふくまれています。ホウ酸団子はとても危険ですので乳幼児がいる家庭では置かないようにしてください。 |
| キッチンハイターなどの漂白剤 | 食器を漂白剤に漬け置きしていると、誤ってそれを飲んでしまうことがあります。漂白剤は粘膜を腐らせる作用があるため、原液を飲むと口の中や食道に潰瘍ができ、大変危険です。また食器に漂白剤、カビ取り剤、殺虫剤などを入れていると誤飲事故のもとですので入れないようにしてください。 |
| 大人の薬 | 高血圧や糖尿病の薬は危険です。必ず子供の手の届かないところにしまってください。決してお菓子の缶にはいれないでください。 |
| 灯油 | ポンプをコップに立てておくとコップの中に灯油がたまり、子供が飲むことがあります。灯油は化学性肺炎を起こすので危険です。子供の入らない場所に置くようにしてください。 |
4月

| Q。虫歯の予防は? | A。虫歯は主にミュータンス菌という細菌によっておこります。 ①赤ちゃんはミュータンス菌をもってないのですが、まわりの大人(家族)から感染します。 ②感染時期は1歳半から3歳までの間が最も多いのですが、感染時期が遅くなるほど虫歯になりにくいと考えられています。 ③ミュータンス菌の感染を防ぐためには子供さんだけでなく家族全員が虫歯の治療・歯磨きの励行により口の中を清潔にすることが大切です。 ④子供さんに対しては、以下のことが効果的です。 歯磨きの習慣づけ・良く噛む習慣づけ(唾液の分泌が増え虫歯予防につながる) 規則正しい食事・フッ素の利用 (フッ素の利用は1歳から15歳くらいまでが良く、歯科医院でフッ素を塗ってもらうか家庭用フッ素入り洗口剤、ジェル、歯磨き剤を使ってください。) |
| Q.乳歯の歯並びが悪いのですが? | A.4歳までは指しゃぶりや爪噛みなどのくせを直して様子をみます。 4歳を過ぎて歯並びが悪い場合は矯正歯科でご相談ください。 |
| Q.けがで歯が折れたり抜けたりした時は? | A。歯が折れた場合は、折れた歯を持ってすぐ歯科医を受診してください。折れた歯を元どうり治せる場合があります。 A.歯が完全に抜けてしまった場合は、抜けた歯を水道水で洗い、歯を口の中に含んでおくか牛乳につけてできるだけ早く歯科を受診してください。 *抜けた歯が元に戻るためには歯の歯根膜という部分が生きてないといけません。 歯根膜は乾燥に弱いので空気中で30分くらいしか生きられません。歯を口の中に入れておくか牛乳に漬けておくと数時間歯根膜を生かすことができます。ティッシュにくるむと乾燥が進んで歯根膜が早くだめになるので決してティッシュにくるんではいけません。 |
3月
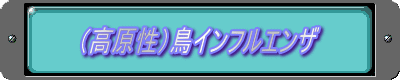
鳥に感染するインフルエンザは人のインフルエンザとは異なったウイルス『鳥インフルエンザ』で、
このうち(人にたいしてではない)強い病原性を示すものを『高病原性鳥インフルエンザ』と呼んでいます。
| 高病原性鳥インフルエンザ | ニワトリ、アヒル、七面鳥、うずら等が感染すると全身症状をおこし、大量死もまれではありません。渡り鳥(特にノガモ)は鳥インフルエンザに対して抵抗力があり、感染源と考えられています。 |
| 人にもうつるんだ? | めってに人には感染しないと言われていましたが、今冬にタイ、ベトナム、中国などで感染が報告され大問題となっています。鳥から人への感染は病気になった鳥と近距離で接触した場合、またはそれらの内臓や排泄物に接触した場合がほとんどで、鶏肉や鶏卵からの感染報告はありません。 |
| ワクチン | 現在、人に使用されているインフルエンザワクチンは人の間で流行しているインフルエンザに対して効果はありますが鳥インフルエンザには効果はありません。 |
| 検査方法 | 鳥インフルエンザはヒトのA型インフルエンザウイルスの診断に使う迅速診断キットで検査することは可能ですが本当に感染しているかどうか調べるためには専門機関で特殊検査が必要です。 |
| 治療 | A型インフルエンザの治療に用いられている抗インフルエンザ薬は有効です。 |
| 感染予防 | 通常の生活の中では特別な予防を行なう必要はありませんが ①鳥インフルエンザの流行がみられている鶏舎などにはちかづかない・②ペットとして飼育している鳥については、野鳥との接触を絶ち鳥のまわりを清潔にする。③不審な死に方をした鳥を見つけた場合決して素手で触らないようにし保健所などに通報して指示をあおいでください。 ★インフルエンザウイルスは洗浄に弱いので手洗いと清掃の励行が効果的です。 ★インフルエンザウイルスは加熱(75度で1分)により死滅しますので過熱して食べれば問題ありません。 ★流行している国へ旅行する場合は生きた鳥類のいる施設や市場への立ち寄り接触は避けましょう。 |
| 新型ヒトインフルエンザの危険性 | 通常のヒトインフルエンザウイルスと高病原性鳥インフルエンザに同時に感染すると、両者の間でウイルス遺伝子の再集合がおこり『新型ヒトインフルエンザ』が発生する可能性があるため世界中が警戒しています。 |
2月
現在、インフルエンザとともに嘔吐下痢症が流行しています。嘔吐下痢症はウイルスが原因で起こる腸炎です。現在流行している嘔吐下痢症の症状はあまりつよくありません。突然吐き始めますが、嘔吐は半日ほどで治まります。その後下痢が3〜4日続きます。熱は約半数の人でみられ38度位までのことが多いようです。便が白っぽくなる場合は症状が強く嘔吐や下痢が長引いたり高熱が出たりします。
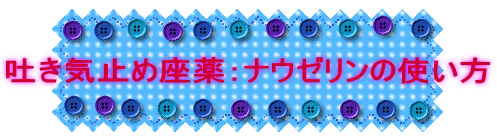
| 使い方 | 座薬を入れて30分から1時間すると効果がでてきますのでお茶やイオン飲料などの水分を与えてください。水分をとっても吐かないようなら固形食を与えてかまいません。吐き気が止まっても吐き気が続くようなら8時間あけて2回目をいれてください。 |
| 薬容量 | ナウウゼリン座薬は10戸30と60(大人用)の3種類あります。 *6㎏〜9㎏の乳児・・・・・・・・ナウゼリン10を2/3個 *10㎏〜13㎏の幼児・・・・・・ナウゼリン10を1個 *14㎏〜15㎏の幼児・・・・・・ナウゼリン30を1/3個 *16㎏〜19㎏の幼児・・・・・・ナウゼリン30を2/3個 *20㎏以上の学童・・・・・・・・ナウゼリン30を1個 |
| 注意 | ①腸重積、腸閉塞などの病気ではナウゼリン座薬を入れても嘔吐はとまりません。受診ください。 ②ナウゼリンシロップ(内服薬)と同時に使わないようにしてください。 ③保存は室温でOK。(冷蔵庫に入れる必要なし) ④副作用としてまれにアレルギー症状、筋肉の硬直などがみられることがあります。 |
1月
![]()
![]()
| 原因 | RSウイルスによる感染症で、気管支の奥の細気管支というところに炎症が起こります。 |
| 1歳以下の子供に多くみられます。 | |
| 症状 | 冬に多く、最初は鼻水や咳などの軽い風邪症状だけですがその後 咳がひどくなり苦しそうに咳き込むようになります。 そして、ぜーぜーひーひーという喘鳴や 鼻翼呼吸(息をするたびに小鼻をぴくぴくさせる) 陥没呼吸(息をするたびに首や胸のしてが引っ込む)がみられ、呼吸困難に陥り体や唇の色が悪くなります。 |
| 注意 | 呼吸が苦しそうなときは入院して酸素吸入,点滴などの治療を受ける必要があります。 手遅れになると命にかかわりますので呼吸が苦しそうになったらすぐに病院を受診してください。 |
![]()
![]()
| 風邪をひいた時に喘息に似たゼイゼイという喘鳴や呼吸困難を起こす病気です。 | |
| 1歳から3歳の幼児に多くみられます。 | |
| 症状 | 気管支の炎症や分泌物のために空気のとおりが悪くなり 喘鳴が起こります。 喘息様気管支炎は気管支喘息とは異なる病気ですが、将来喘息に移行することがあるので 注意が必要です。 |
| 薬 | 痰が切れると症状が軽くなるので 気管支拡張剤と去痰剤を処方します。 気管支喘息の時に処方するテオドールを使うこともあります。 |
| 注意 | ゼイゼイいっても食欲があり機嫌よく遊んでいる場合は心配ありませんが、息苦しそうにしている時は病院を受診してください。 |